そもそもLive2Dモデルを知識&スキル0の素人が1から作成可能なのか?
まず結論としては可能です。
元の立ち絵については生成AIを活用すれば誰でも高品質なイラストを作ることが可能です。ただし、生成AIに使用するモデルが他者の権利を侵害していないかの配慮とNVIDIA社製のGPUを搭載したそこそこ高性能なPCは必要です。なぜAMD社製のGPUではダメなのかというと、ローカルで動作する生成AIツールはNVIDIA社製のGPUに最適化されている場合がほとんどで、AMD社製のGPUは対応していない場合があるからです。ちなみにChatGPTやSeaArtなどの外部のサーバーで動作するAIツールでは高品質で差別化されたイラストを作ることは難しいので、やはりローカルでAIを動作させる環境は必要だと思います。ということで、立ち絵は生成AIを使用することで用意できます。次に立ち絵をパーツ分けしてPSDファイル形式で保存する必要がありますが、これもデジタルイラストツールを使用すれば割と簡単にできます。無料で使用可能なデジタルイラストソフトとしてはメディバンペイントが有名ですが、かなり多機能なソフトなのでUI等の使い方を勉強してからじゃないと難しいと思います。王道はCLIP STUDIO PAINTかPhotoshopですかね。どちらも月額のサブスクタイプなので、短期間の利用のみならむしろ安く済むかもしれません。あとは環境に応じて、ProcreateやSAI、アイビスペイント等が使用可能です。わたしはアイビスペイントを使用しています。理由はUIが最もわかりやすく、イラスト素人でも簡単に使えるからですね。立ち絵をパーツ分けする具体的な方法ですが、立ち絵の画像ファイルを任意のデジタルイラストツールで読み込んだ後、パーツ分けしたい部分を投げ縄ツールなどで囲んで、別のレイヤーにコピーした後、不要な部分を消しゴムで自力で地道に消していきます。この作業はほぼぬり絵です。デジタルなためバカみたいに画像を拡大可能なので、時間をかければだれでも綺麗に欲しいパーツのみを切り出すことが可能です。ただし、後ろ髪とか耳などの一部が隠れてしまってる部位は適当に書き足す必要があります。ただ、これもなんかテキトーにやればなんとかなります。雑に直しても遠目に見たら全然気にならないレベルなので大丈夫です。画像のPSD化もレイヤー分けした状態でファイル形式を選んで保存するだけです。ということでパーツ分けした立ち絵のPSDファイルも自力で用意できます。最後に作成した立ち絵のPSDファイルをもとにLive2Dモデルを作るわけですが、これには株式会社Live2D公式のLive2D Cubism Editorというソフトを使用します。このソフトは無料では中解像度の画像まで使えて、インストールから一定期間までは高解像度の画像を扱える有料プランをお試しで利用可能です。このソフトの使い方は初見ではちんぷんかんぷんですが、ありがたいことに使い方から設定およびLive2Dモデルの作り方まで丁寧に解説されている動画がYouTubeにアップロードされているので、それを見ながら真似するだけで誰でもLive2Dモデルは作ることが可能です。ポイントとしては、あらかじめ参考にするYouTubeの動画は決めておいて、その動画で解説されているモデルと同じパーツ分けとなるようにあらかじめ準備しておくと良いです。なんなら、参考動画よりもパーツの種類は少ない方が簡単に作れます。ということで、あら不思議ちょっと勉強するだけでVtuberのLive2Dモデルって実は素人でも時間をかければ大したスキルが無くても作れてしまうんですね。まあ、さすがにこの記事だけ見て作るのは無理ですが、上記で私が記述した内容の詳細はYouTubeで解説動画を探せば全て見つかります。実際、私はググらずに全てYouTube上の動画のみを参考にしてLive2Dモデルを自作しました。参考までに作成したモデルの動画を載せておきます。
補足
そういえば以前、VtuberのLive2Dモデルの作り方については簡単にまとめた記事を投稿していたので、一応リンクを下の画像に用意しておきます。
VtuberのLive2Dモデルを自作するメリット5選
その1:あらゆる意味で自由度が高く、他人に迷惑がかからない
ここからが本題ですが、まず一番のメリットは自由ってことですね。これはデザイン等もそうですが、なによりYouTubeで活動する上での自由度が高いのが魅力ですね。Live2Dモデルを外注する場合、立ち絵のイラストレーターの方とLive2Dモデル製作者の方との人間関係が構築されてしまうため、その両方に迷惑がかからないようにYouTubeでの活動は常に潔白である必要があります。そこら辺の配慮が必要ってことですね。これはイラストレーターの方とLive2Dモデル製作者の方のネームバリューが高ければ高いほど、気をつかう必要が出てきます。例えば、企業からの依頼で製作経験のあるような有名な方に依頼した場合、後々に自分が何か過失があることをしでかしてしまった場合、製作者はおろか最悪同じ製作者が担当された他の企業Vtuberに迷惑をかけてしまうかもしれません。下手したら、その企業から損害賠償を請求される可能性すらありますよね。わたしはこの辺のリスクを考慮して有名なイラストレーターの方に製作を依頼することは断念しました。実は仮見積もりを依頼するための仕様書(仮)までは作っていたんですけどね。仕様書(仮)の内容を推敲している間にリスクに気が付いて辞めました。あとはLive2Dモデルをココナラやnizimaで外注することも考えましたが、こっちもあまりメリットを感じなかったので結局自作することにしました。
その2:安い
これは当然ですが、全部自分でやるので費用は極限まで安くなります。例えば元のイラスト立ち絵を有名イラストレーターに依頼する場合、100万~200万円が相場らしいですね。さらにLive2Dモデル製作に20万~30万円くらいはかかります。ココナラやnizimaで外注する場合、立ち絵からモデル製作まで一式で20万円~50万円が相場ですね。ここら辺の費用がほぼ0円になるのは、でかいといえばでかいですかね。まあ、本気でVtuberやるなら100万、200万程度はポンと出す覚悟は必要な気もしますね。少なくとも登録者50万人とか100万人を目指すなら、Live2Dモデル製作をトッププロに依頼するのは必須だと思います。そうじゃないなら、自作でよくね?って感じです。正直、クオリティで言えば私が紹介したやり方なら、たいていの個人勢VtuberのLive2Dモデルよりもハイクオリティなモデルが作れると思います。
その3:左右非対称のモデルが作れる
これはどういうことかというと、基本的にVtuberの立ち絵はアクセサリーや腕がしっかり描かれている場合を除いて、左右対称で描かれることが多いんですよね。これはなぜかというと、後でLive2Dで動きの設定をするときに左右対称だと一部をコピペしたりして工数を削減できるっていうのがあります。あと、立ち絵の段階で顔が少し横向いてたとしたら、それを上下左右に動かしてパーツを変形させるとき、考慮する事項が増えてかなり手間がかかります。あとプロのモデラーの方のセールスポイントって、モデルを高可動でダイナミックに動かすことができるっていうところなんですが、左右非対称のイラストを高可動でモデリングするのは相当難しいですね。だから、多分ですけどモデル製作を外注する場合、左右非対称で依頼するんだったら割り増し料金を取られるか、そもそもモデラーさんが対応してくれない可能性があります。じゃあ、自作なら左右非対称のモデルを作れるのか?っていうと。可動変位を控えめにして低可動のモデルにすれば可能なはずです。ただし、アオリやフカンなどのイラストの知識は多少なり必要になってきます。実際、私が自作したモデルは左右非対称で若干右を向いているモデルなのですが、素人がテキトーにやってもそれなりに違和感なく動かすことに成功しています。だから100%の保証はできませんが、多分できます。てか、そもそも左右非対称にする必要あるの?ってところですが、雑談とか歌とかがメインなら左右対称で正面向いたモデルの方が良いと思います。一方、ゲーム配信がメインの場合はモデルを右下に配置することになるので、モデルはやや右を向いている方がバランスが良いかなと個人的には思います。あと左右対称の正面絵は元のイラストのクオリティが低いと、クオリティの低さがより際立つので、ハイクオリティの立ち絵じゃなければちょっと横向いていた方がアクセントがついて、のっぺり感が薄れて良い絵に見えると思います。タレントとか声優の人が写真に撮られるとき、いっつもこの人顔が少し横向いて同じ角度だなってことがあるんですが、やっぱり人間の一番のキメ顔って真正面顔じゃなくてちょっと横向いた顔なんですよね。あと、個人勢Vtuberの人たちはマジで左右対称モデルの人が多いので、それとは差別化できるって点も高評価ですかね。
その4:ポーズと表情が違う立ち絵が作り放題
ポーズが違う立ち絵がなぜ複数必要かというと、サムネ用ですね。ちゃんとしたサムネを作ろうとした場合、自身のモデルのポーズや表情が異なるイラストが沢山必要です。サムネのイラストが同じだと、ズラッと並べたときに代わり映えがしなくてショボくみえてしまいますし、なんかこいつやる気ないのかな?って思われてしまいます。だから、数字持ってるVtuberの人たちはポーズや表情の異なるイラストを別で外注して用意しています。これには追加の費用はもちろんですが、時間もかかります。必要に応じて、元イラストとは別のイラストレーターの方に作成依頼する必要もあるでしょう。そしたら、また追加で人間関係が生じてしまいます。その点、自作でローカルの生成AIを使えば、設定次第では同じ顔、同じ衣装、時には別の衣装にして色んなポーズイラストを作りたい放題です。これはメチャクチャ便利ですね。YouTubeで活動する上でサムネは超重要ですので、そのカスタマイズ性が大幅に向上するのは自作の大きなメリットだと思います。
その5:クリエイターを名乗れる
これはおまけみたいなもんですが、生成AIを利用するとはいえ、イラストをパーツ分けしてLive2Dモデルを製作するのは立派な創作活動だと思います。少なくともLive2Dモデルを製作するスキルは身に付きますし、1体作れれば同じように別のモデルを作れるようになっているはずです。なんならもうちょっとスキルを磨けばセミプロとしてココナラやnizimaでLive2Dモデル製作者として出品して稼ぐことも可能かもしれません。まあ、費用対効果的にはあまりおすすめはしませんが。とはいえ2次元の作品で創作体験ができるのは得難い経験だと思います。あと、時間はかかりますが創作活動ってやっぱりやってて楽しいですね。別に作品が完成した時に大きな達成感とかはなかったですが、単純に自分のVtuberのLive2Dモデルを自分の力で作るというのが楽しくて仕方がなかったです。正直、時間に余裕があるなら別のモデルも作ってみたいとさえ思っています。
VtuberのLive2Dモデルを自作するデメリット2選
その1:生成AI使用はリスクが高い
これはそんなに説明はいらないかもしれませんが、生成AIの使用は生成AIという時点で非難や攻撃の対象となる可能性があります。一応、説明しておくと基本的には生成AIツール自体には全く違法性はありません。例えば私が使用した生成AIツールはStable Diffusionなのですが、このツール自体の基本機能には何らかかの著作物を繰り返し学習するような機能はありません。ただ、外部から入力された「チェックポイント」という基礎データファイルをベースに各種設定値や入力コマンド(プロンプト)をもとに画像を生成するだけのツールです。ただしですが、上記の「チェックポイント」に問題がある場合があります。基本的に「チェックポイント」は外部の専用のサイトで有志の人達が作成してアップロードしたファイルをダウンロードして使用するのですが、利用者側からはアップロードされている「チェックポイント」がどのように作成されているのかを知る術がありません。仮にその「チェックポイント」が何かの著作物を無断で学習して作られたものだとしたら、使用には問題があると個人的には思います。しかし、実際に問題があるかどうかわからないので、大丈夫そうな「チェックポイント」を選んで使用するしかないのが現状です。実際、「チェックポイント」のダウンロードサイトを見ると、サンプル画像がアニメや漫画の原作絵とそっくりなものもあるので、少なくともそういうのは使用は避けるべきだと思います。あと、上記では「ツール自体の基本機能には何らかかの著作物を繰り返し学習するような機能はありません」と記述しましたが、追加であるプラグインを導入すれば自分が選んだ画像を学習させて、生成AIの結果に反映させることも可能です。この自分で画像を学習させる行為はその画像の作成者の許可があれば問題ないでしょうが、無許可でやるのは非常にまずいと思います。
ということで、生成AIツールを使用する以上、完全な白であり清廉潔白であることを主張することは困難です。というか、自分が作成したLive2Dモデルに問題があろうがなかろうが、「生成AI」というだけで攻撃してくる人間はネット上にはごまんと存在します。YouTubeでのコメントやX、ブログなどであれこれ言われたときにどう対処するかは、あらかじめ考えておく必要があるというのが大きなデメリットですね。
その2:高可動のモデルは作れない
これは素人の限界ですね。さすがにプロのモデラー並みにイラストを動かすのは至難の業です。Live2D Cubism Editorでの作業では3種類の異なる軸に分けて各パーツを動かしたり、変形させてモデルの動きを実装します。この時、大きく動かそうとすると、当然各パーツの変位も大きくする必要があるので、イラスト関係の知識が薄いと各パーツをどれくらい動かして、どれくらい変形させればよいのかわからなくなります。そして先ほど3種類の異なる軸に分けて設定すると述べましたが、最終的には全ての軸で同時に動かすことになるので、そこで必ず破綻する箇所が発生します。この破綻具合も、モデルの可動幅が大きくなるほど悪化していくので修正が大変です。なので、結論としては素人は欲張らずにモデルの動きは小さくして、高可動は潔く諦めるのが良いと思います。
まあ、個人的には高可動のモデルってそもそも必要か?って疑問もあります。高可動の方がVtuberの感情がダイナミックに伝わって、配信が盛り上がるってアピールがされてますが、言うほどか?と思ってしまいます。結局はVtuberにとってLIve2Dモデルって、大本のイラストの基礎デザインの美麗さが一番大事で、モデルの動きはある程度実際の動きに追従してくれたらそれなりの出来でも満足できるなー、というのが個人的な感想です。
まとめ
ということでVtuberのLive2Dモデルを自作するメリット5選とデメリット2選について、詳細を書きなぐった記事でした。まあ自分で読み返しても、この記事見て「よし!自分もいっちょVtuberのLive2Dモデルを自作してやろう!」と思う人間はそうそういないんじゃないかと思いますが、一つの選択肢として自作もアリだということは認識して貰えたらうれしいです。多分世間の常識では、「VtuberのLive2Dモデルはプロに依頼するもの」という固定観念があると思うので、それを覆してやりたいなと思うわけですよ。まあムリなんですけど。もっとガチで徹底的に自作の手順と方法を解説することもできるのですが、さすがにブログだと長くなりすぎるので、やるとしても動画をシリーズで作って、YouTubeにアップロードするかなーって感じです。ただ、さすがにシリーズでHow toの動画を作るのは大変すぎるので、やるとしてももうちょっと名が売れて有名になれてからですかねー。
はい、ということで今回はここまでです。長々とお付き合いいただきありあとうございます。良ければ別の記事を見たり、YouTubeのチャンネルに遊びに来て貰えたら幸いです。それではー ( ̄▽ ̄)ノ
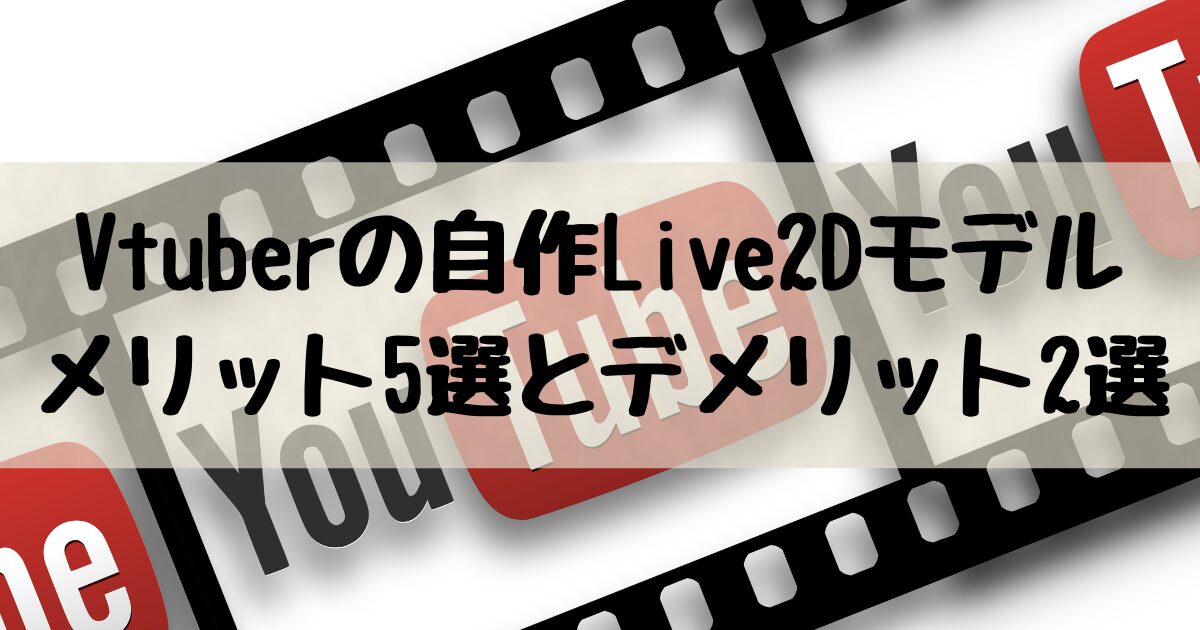
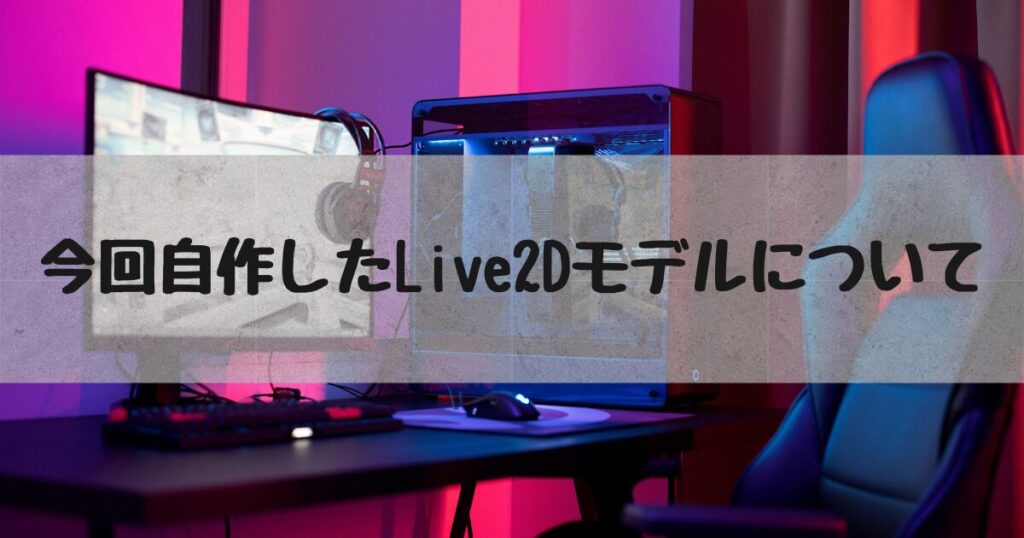
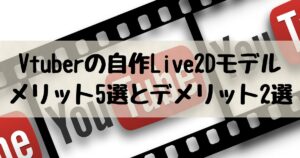
コメント